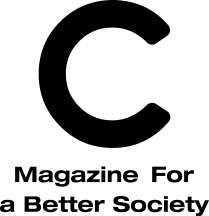日本の飲酒文化は海外からどう見られているのか。日本社会と飲酒に関する著書を持つ米ローズハルマン工科大学のポール・クリステンセン准教授は、「人前で泥酔することが当然だとされているのは日本独特だ。日本の飲酒文化は男らしさと密接に関係があり、女性の出世を妨げる一因にもなっている」という――。(第1回/全2回)(取材・文=NY在住ジャーナリスト・肥田美佐子)
――日本は、世界で最も「飲酒に甘い国」「お酒フレンドリーな国」とも言えます。クリステンセン准教授が研究や著書で、飲酒に対する日本社会の寛容さや緩さを指摘するように、日本では路上などでの飲酒が許されており、ビジネスマンが電車の中で酔いつぶれたり、駅のホームや車内、路上で吐いたりといった光景も日常茶飯事です。なぜニッポンの飲酒文化に興味を抱いたのですか。
1995年8月、17歳の頃に初めて日本を訪れたことが、そもそもの始まりだ。ある夜、アメリカ人の先輩や仲間たちとバーに行ったところ、店員は、アメリカの店のように年齢を確認することもなく(注:アメリカの飲酒年齢は21歳)、注文したビールを運んできた。誰も私の年齢など気に留めていない様子だった。これには仰天した。
そして、「なんてエキサイティングなんだ!」と感じた。17歳の若者の目には、日本は「実にイケている」国に映った。
その後、アメリカの大学で日本語や日本文学・文化などを学びながら、日本への関心を深めていった。そして、(大学を卒業した)2000年に初めて日本に住んだ時は、成人として、年齢を気にすることなく飲み歩いた。
そして、それから数年後、アメリカの大学院に通っていた頃、日本のバーや居酒屋での豊富な飲酒体験を基に、日本の飲酒事情について研究してみようと考えた。というのも、日本のような(飲酒が盛んな)国で、その傍流にいる、お酒が飲めない人や飲みたくない人はどうしているのだろうという関心が頭をもたげたからだ。
日本は世界から見ると、飲酒にとても寛容な国だ。公の場でも飲酒が許され、自動販売機でもお酒が買える。
その一方で、アルコール依存症から立ち直ろうとしている人や、アルコール依存症だと自覚している人がいる。また、飲みたくないにもかかわらず、周りに合わせなければという重圧を感じている人もいる。だが、そうした人たちは、日本では「見えない」存在であり、日本社会の別の面を映し出している。
そうした、日本社会に内在する「矛盾」が私の関心をかき立て、研究と自著『Japan, Alcoholism, and Masculinity: Suffering Sobriety in Tokyo』(『日本、アルコール依存症、そして、男らしさ 東京で断酒しようと苦闘する』(仮題・未邦訳、2014年12月刊行)の執筆につながった。現在も、日本の飲酒問題には大きな関心を持っている。
――日本の飲酒文化の中で、どのような面に最も衝撃を受けましたか。
まず、日本では、人々が「公の場で泥酔する」ことを前提にしたインフラが築かれていることだ。(特定の機会だけでなく)年がら年中、人前で酔っぱらうことについて、その是非すら問うことがない。人々が酔っぱらうことを前提にしたインフラが見事なまでに整備されている。例えば、駅に備え付けられている「吐瀉物専用掃除機」が好例だ。
また、私が過去十何年間、日本に行くたびに撮り続けている駅のポスターもそうだ。JRや地下鉄の駅には、「酔落注意!」「転落注意」「危ないっ‼」といったポスターが何枚も貼られている。1年前、東京に滞在した時に撮ったポスターには、「ホームで起こる人身傷害事故のうち、2人に1人がお酒に酔ったお客さまです」と書かれている。
「お酒を飲んだら、ホームから落ちないよう気を付けましょう」「危ないと思ったら、迷わず非常停止ボタンを押してください」といった呼びかけは、とてもいいと思う。だが、「そんなにしょっちゅう、こんなことがあっていいのか」「自分の命を危険にさらすほど深酒をすべきなのか」という根本的な問いかけは決してなされない。
つまり、ホームから落ちるほど飲みすぎる乗客がいることを前提にポスターが作られているのだ。
日本の飲酒対策用インフラの充実ぶりには目を見張るものがある。とはいえ、そもそも人前で泥酔すること自体に疑問を呈さないのはいかがなものか。私が日本の飲酒文化で衝撃を受けたのは、この点だ。衝撃という言葉が少し大げさだとしても、その点に間違いなく興味をそそられた。
――『日本、アルコール依存症、そして、男らしさ』(仮題)の序文によると、あなたは、「日本でアルコールがどのように消費され、規制されているか」に関心を持ったといいます。そして、「人々が驚くべき頻度で深酒し、駅のホームで吐いたり、公の場で酔っぱらったり、至る所で酔いつぶれて寝込んだり」しても、誰も気に留めず、駅員が淡々と掃除するだけだという事実にも興味を持ったそうですね。
日本を外から眺めると、そう見える。そう感じるのは、アメリカ人だけではないだろう。もちろん、世界のどの国でも、酔っぱらう人々はいる。特に大きなイベントなどがあれば、そうだろう。例えば、アメリカだったら、2月初めに開かれるアメリカンフットボールの一大祭典「スーパーボウル」だ。
しかし、日本では、それが日常的に起こる。木曜日や金曜日、土曜日の夜ともなると、東京など、多くの主要都市で人々が泥酔し、自著の中で説明したような光景が繰り広げられる。私には、それが驚きだった。日本を訪れる外国人の多くも、ひとたび夜の街に繰り出せば、同じように感じるはずだ。
――日本社会では、街中や駅のホーム、車内で酔いつぶれることが容認されています。
問題は、どこまでが正常で、どこまでが容認されるべきなのかという、人々の見方だ。毎晩、そうした光景を目にしていたら、それが生活の一部であるかのように思ってしまう。そして、何の疑問も持たなくなる。
飲酒問題について考えることは、(お酒をポジティブに捉える)日本社会、そして、その社会的期待に疑問を呈することを意味する。それが、日本の人々が飲酒問題で直面している本質と言える。
――昨年末、ニューヨーク・マンハッタンの中心にある繁華街「タイムズスクエア」を何ブロックも歩きました。人であふれ返っていましたが、東京の街と違い、飲みすぎによる吐瀉物と思われるようなものは見かけませんでした。
まず、日本ではアメリカと違い、アルコールへのアクセスが容易だという構造的な問題がある。
注:アメリカでは、日本と同様にアルコール購入における年齢確認が制度化されている。加えて、酒類の自動販売機はなく、ニューヨーク市をはじめ、大半の都市で、路上や公園といった公共の場での飲酒が法的に禁じられているなど、アルコールへのアクセスに制限がある。
また、日本では、飲みすぎて駅のホームや居酒屋の店内などを汚しても、駅員や店員が掃除をしてくれることが前提になっている。駅などを汚す人が多いのは、こうした認識によるところが大きいのではないか。
ニューヨークをはじめ、人口が多い主要都市では、地下鉄など、公共交通機関の車内で吐こうものなら、目を付けられ、狙われる可能性がある。一部の乗客が怒り出したり、不快に思ったりし、自分の身を危険にさらすことになりかねない。
――書籍の第2章「聖なるお酒」には、日本では、男同士でお酒を飲むことが「男らしさ・男性としての強さ」を意味すると書かれています。そして、力強さの象徴である、著名なスポーツ選手をアルコールのコマーシャルに起用することが飲酒に対する寛容な見方を助長する、と。日本で、アルコールの消費と男らしさ・男性としての強さを結び付ける文化が生まれた背景を教えてください。
ひと言では説明しがたい。例えば、同じ日本でも、地域によって、その二つが、より密接に結び付いているとされる所もある。男同士で杯を酌み交わしながら交流を深めることで、アルコールが、社会的な絆を保つ「接着剤」のような役割を果たしているのだ。
一方、日本全体に目を向けると、第2次世界大戦以降、1960年代から80年代にかけて、日本経済が目を見張るような成長を遂げ、右肩上がりだった時、「サラリーマン」を中心とする男性社会と飲酒文化という特別な構造が出来上がった。
男性が一家の大黒柱として、お金を稼ぎ、専業主婦の妻が家を守るという役割分担の下で、男たちは終業後、街に繰り出し、大いに飲んだ。今日も一日、一生懸命働いた自分への「ご褒美」として。そして、仕事仲間との絆を深め、人間関係を円滑にし、一丸となって、より大きな成果を上げるための「手段」として。
日本が敗戦から立ち直り、再建される過程で、そうした役割分担が強化された。そして、汗水垂らして働いた後はお酒で男同士の結び付きを深める、という考え方が社会に根付き、当たり前のことになった。
1990年代初めのバブル崩壊後、お金のかかる飲み会の機会が減り、そうした考え方に若干疑問が呈され始めたとはいえ、まだまだ健在だと思う。日本で、飲酒と、男としての強さという概念が戦後の高度経済成長と結び付いていたことに、大いに興味を引かれる。
――アルコールの消費と男らしさ・男性としての強さを結び付ける文化は日本独特のものなのでしょうか。
形は違うが、そうした文化は多くの国々で見受けられる。もちろん、アメリカにも、一部の大学生の間で見られるような「大量飲酒文化」はある。もっとも、日本の飲酒文化ほど「ジェンダー」色は強くないが。
ところで、質問に出てきた「独特」を意味する「unique(ユニークな)」という言葉だが、私たち文化人類学者は、こんなジョークを飛ばす。「『unique』という言葉は好きじゃない。世の中には唯一無二のものなどなく、必ずほかの何かが見つかるからだ」と。そうした意味では、この場合、「distinct(特徴的な、明白な)」のほうが、しっくりくるかもしれないね。
ほかの国にも「大量飲酒文化」はあるが、日本における飲酒と男らしさの結び付きは非常に強固だ。
――とはいえ、アメリカ映画で、若い男性が大勢集まって、ビールを片手にテレビのスポーツ番組を見て歓声を上げるシーンをよく見かけます。日本の飲酒文化とはどこが違うのでしょう?
日本でお酒を飲んでいる人たちを見ると、まず不思議に感じるのが、自分が酔っていることを隠そうとせず、素直に表に出す点だ。泥酔するまで飲むことがゴールであるかのように、酔っぱらうことを問題だと思っていないようだ。この点がアメリカと違う。
アメリカでは、特に男性は「酒に飲まれてはいけない」という意識が強い。お酒をたくさん飲んでも、まるでしらふのように自分を保つことができなければならないのだ。つまり、アメリカの流儀に従えば、量は飲めるが、酔っているように見えない人が「グッド・ドリンカー(良きお酒飲み、たちのいいお酒飲み)」とされる。
ひるがえって日本では、その真逆に近い。さほど飲んでいない人も「いかに酔っているか」を強調するかのごとく、大声で笑ったり、羽目を外すような行動を取ったり、むしろ大げさに振る舞う姿が目立つ。そして、いったん会計が済むと、酔いがさめたかのように落ち着く。
日本では、飲みに行くからには、酔っぱらって大いに楽しみ、仲間との絆を深めることを重視する。一方、アメリカでは、「俺はたくさん飲めるが、何ら変わらない。大声で笑ったり、千鳥足になったり、泣き出したり、感情をあらわにしたりするようなことはしない!」となる。
文化をはじめ、ジェンダーや飲酒をめぐる考え方について、日米には大きな開きがある。
――アメリカでは、スーツに身を包んだビジネスマンが飲みすぎて、駅のホームや車内、街中で戻したりしませんよね?
アメリカでビジネスマンがそんなことをしたら、「弱さ」だと取られてしまう。もちろん、日本でも、車内には悪臭が立ち込めるし、飲み過ぎて人前で失態を演じることは問題だと思われているだろう。とはいえ、そうした状況が「起こる」ことが前提になっている。誰かが今夜も気分が悪くなるほど飲みすぎるだろう、と。
日本では、そうした行為に対し、アメリカよりはるかに批判的な見方が少ない。
――日本では「接待」と称し、取引先と「飲み会」をする文化があります。また、上司や同僚などとのアフターファイブの飲み会が昇進や出世に有利に働くこともあります。日本の飲酒文化は、「男同士の絆」や閉鎖的な男性社会の形成を助長するという意味で、女性の出世の足を引っ張っている存在だと言えるのでしょうか。
おそらく、そう言えるだろう。日本では「飲みニケーション」と言われていると聞く。日本の男性は特にそうかもしれないが、中にはコミュニケーションが不得意な人もいるため、アルコールが必要になるという面もある。
また、日本の場合、男性がお酒を飲む場所は往々にしてジェンダー色が強い。居酒屋はそうでもないだろうが、例えば、「スナック」がそうだ。一般的に、お店でお酒を出すのは女性、飲むのは男性であり、非常に不平等な関係と言える。
日本でも、ボーイズクラブ(閉鎖的な男性社会)の存在に疑問を呈する声がいくらか出ているかもしれないが、依然として健在だ。それゆえ、企業における女性の出世に足かせがはめられてしまう。
男同士の飲み会など、ボーイズクラブの存在だけが日本女性の出世の阻害要因かどうかはわからない。だが、日本企業にはジェンダーと仕事に対する旧態依然とした姿勢が見られ、それが大きな問題をはらんでいる。
ジェンダーの点から見ると、日本は世界で最も平等度が低い国の一つだと認識している。日本の文化と飲酒をめぐる慣行が、その原因の一部であることは確かだ。
――アメリカでは、企業における女性管理職の割合が40%を超えているのに対し、日本企業は、調査によって数字にやや幅はありますが、約10~12%です。専業主婦の女性が子供の面倒を見てくれなければ、男性は頻繁に夜遅くまで飲めませんよね?
そうだ、構造的な問題だ。日本における男性の飲酒慣行は、妻や夫の母親などが家で子供の面倒を見ることを前提とした社会システムの上に成り立っている。そして、それは女性に、望まない選択を強いることが多い。男同士の飲み会は、こうしたシステムの中に組み込まれている。
故安倍晋三元首相も岸田文雄首相も、女性の活躍をめぐり、何らかの見解を述べているが、そうした発言は有権者受けがいい。実際のところ、どれほど本気で変革しようと思っているのかは疑問だ。
もちろん、アメリカでも、業界や場所によっては、日本の状況といくらか似ている場合もあるだろう。育児の状況は国を問わない。多くの国々で妻と夫がまったく平等に育児に関わっている、などとは思わない。
とはいえ、例えば、私の場合、このインタビューの前に子供2人を学校に迎えに行ってきた。そのせいで、インタビューに遅れるのではないかと気が気でなかった。日頃から、できる限り妻と平等に育児を分担するよう努めているが、それでもまだ足りないと、恥ずかしく思っている。
(後編へ続く)
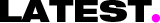

連載:人生二毛作
南米コロンビアへ!! 【連載第3回】
直行では行けない南米 シカゴからコロンビアへ飛ぶ飛行機はマイアミで乗…
2026.03.04 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第5回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2026.02.07 UP

連載:人生二毛作
映画の街 シカゴ!【連載第2回】
まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…
2025.11.21 UP

連載:人生二毛作
世界一周旅、出発の序章 【連載第1回】
さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…
2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント 開催決定!
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に
定期観察 |連載第10回
先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…
2025.07.30 UP
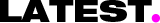

連載:人生二毛作
南米コロンビアへ!! 【連載第3回】
直行では行けない南米 シカゴからコロンビアへ飛ぶ飛行機はマイアミで乗…
2026.03.04 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第5回】自分とク…
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2026.02.07 UP

連載:人生二毛作
映画の街 シカゴ!【連載第2回】
まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…
2025.11.21 UP

連載:人生二毛作
世界一周旅、出発の序章 【連載第1回】
さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…
2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とク…
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に
定期観察 |連載第10回
先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…
2025.07.30 UP
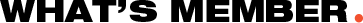
CのMEMBERになると、
オンラインコミュニティでの
MEMBER同士のおしゃべりや
限定コラムやメルマガを
読むことができます。
MEMBER限定のイベントに
参加も可能です!