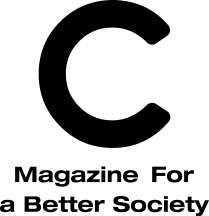「意志が弱い」「快楽主義」といった先入観の下,長年スティグマを押し付けられてきた依存症。「依存症の本質は快感ではなく苦痛の緩和にある」と語るのは,日々の診療にとどまらず治療プログラムの開発や保健行政機関と連携した地域での活動など,多方面で依存症治療に尽力を続ける松本俊彦氏だ。医師は,行き場のない苦痛の緩和を依存に求める患者,そして彼らへのスティグマに対して何ができるのか。今春より精神科医として歩み始めた古賀公基氏(長崎大)が松本氏にインタビューを行った。

古賀 IR誘致などで注目が集まる中,依存症治療の需要は増加し今後さらなる社会問題になると考え,危機感を抱いています。そんな折,先輩医師に紹介されて松本先生の著書を拝読しました。当事者の抱える苦悩やつらさが生々しく描かれ,それに対するアドバイスが実用的で,以来先生のことを私淑しています。
松本 ありがとうございます。
古賀 診療が難しく,苦手意識を持つ精神科医も多い領域だと思います。まずは,先生が依存症治療に取り組み始めたきっかけを教えてください。
松本 実は偶然です。医局人事による依存症専門病院への異動をきっかけに,不本意な形で依存症治療に取り組み始めました。
古賀 「不本意」とは,どういうことでしょう。
松本 依存対象となるアルコールや薬物を絶つよう患者に強制する必要がある領域だと思い,「性に合わない」「嫌だな」と思いました。
一方で,相反するもう一つの気持ちがあり,知らないままでは済まされない領域かもしれないとも感じました。それまで勤務していた神奈川県立精神医療センターで,依存症治療の現場を垣間見ていたからです。第3次覚醒剤乱用期と言われた1990年代半ばの当時,精神科救急には覚醒剤精神病の患者がひっきりなしに来院していました。ただ,精神病の治療は「簡単」で,閉鎖病棟に強制入院させて投薬すれば目に見えて奏功します。だけど,退院してもすぐに戻ってくる。その状況に「懲りないなら逮捕すべきだ」と憤るのと同時に,「覚醒剤をやめられない根っこの問題―つまり,依存症―を解決すべきでは?」とも感じていたのです。
古賀 未知の領域に挑戦する機会としてとらえたのですね。
松本 そう言ってくれると,すごく聞こえがいいね(笑)。おそらく,後者の気持ちは私なりのレジリエンスだったのでしょう。逆境に感じた異動の良い点を探し,自分の中で整合性をとった。当時の私の中にも,依存症領域へのスティグマがあったのですね。
古賀 私自身も,トラウマを背景とする依存症や自傷の領域にスティグマを作ってしまっています。それも自らの経験でなく伝聞の情報に起因するもので,医師として恥ずかしい気持ちがします。患者さんの凄惨な環境や体験に対し,「自分が背負えるのか」「何気ないひと言で傷つけないか」と考えてしまうのです。先生が依存症治療に取り組み始めた当初,恐怖感はありましたか。
松本 ええ,ありましたよ。さらに言えば,心の中をのぞき見たい気持ちと共に患者を傷つけるのではとの恐怖心が,常にありました。通常の臨床ですら怖かったのに,トラウマを持つ患者はなおさらです。
古賀 転機となったエピソードはありますか?
松本 卒後5,6年目に初めて解離性同一性障害の患者さんを診た時です。診察中に別人格が急に出てきて私を恫喝し始め,最も恐怖を覚えた体験でした。ただ,当時神戸大の故・安克昌先生の解離性同一性障害に関する講義を直前に受けていたことが功を奏しました。その講義で学んだ通り,まずは自己紹介をする。そして,どんな人格にも本人を助ける観点で存在理由が必ずあるから,リスペクトを持つ。私は,「お怒りのようですが,担当医としてあなたのことを知りたいのです」と会話を始め,話を聞くうちに相手も怒りではなく次第に悲しみを表出してくれました。そして,一通り対話した後には元の人格に交代してくれた。まさに安先生のおっしゃる通りでした。
古賀 本当に不安なのは,われわれ医師ではなく患者さんのほうですよね。
松本 その通りです。本当に信頼できるのか,患者さんはわれわれを見ています。それを契機に,多剤処方を行っても奏功せず頻繁に救急搬送されるような患者さんでも,話をするうちに徐々に落ち着くことに気付きました。勇気を出して背景にあるトラウマについて聞くと,意外にも「初めて聞いてもらえた」と歓迎される。それが一つの転機になりました。
そのように,診療の中ではブレイクスルーの機会が時々あります。中でも若手の時の印象的な経験は糧になりますよ。私自身,患者さんに怒られながら教わった多くの経験1)が強く印象に残り,現在につながっています。ぜひ,今の時期を大切にしてください。
古賀 依存症の患者が苦しんでいても,医師が共感しにくいのは何が原因なのでしょうか。
松本 私は医学教育に問題があると考えています。学部教育で依存症を学ぶのは,せいぜい精神医学の1講義90分に過ぎませんよね。だから,そもそも依存症に関して医師はほぼ素人です。一方,薬物依存症は回復しないと教える「ダメ。ゼッタイ。」教育は学校教育で年に1回,長年にわたって受けるため学習時間が長い。さらに,依存症からの回復者と接する機会もないので,その印象が医師の中にも刷り込まれたままです。スティグマの大半は,「知らないこと」で作られるのです。
古賀 なるほど。
松本 従来の「患者から離れて診る」「会話しない」から「患者の話を聞こう」との風潮が精神医学全体に広がった現在,依存症の分野だけが遅れています。依存症の本質は快感ではなくて苦痛なのです2)。医師はそこにもっと目を向けてほしい。
依存症の背景には,トラウマの他にも経済状況などの社会的要因も関係します。個人的には,そうした社会的弱者に対する共感性を持つ医師が精神科に多いと考えていますが,あまりにも共感性があり過ぎたり繊細過ぎたりしてもやっていけない。多忙な臨床の中でそういう気持ち,故・中井久夫先生(神戸大)の言う「こころのうぶ毛」がすり減らされますよね。
古賀 そうですね。
松本 そして,自分の物差しで測れる人だけを相手にするようになる。けれど,依存症の臨床では,その態度が実害をなします。治療トラウマと言うべきでしょうか。助けを求めた結果,かえって傷ついた歴史が患者さんの中に刻まれてしまうのです。
古賀 医療者が依存症治療に関して正しい知識を学ぶ方法はありますか。
松本 依存症からの回復者に会うのが一つの答えだと考えています。私も医療者が依存症患者をなぜ忌避するのか長らく疑問に思い,講演のたびに「いい人たちだよ」「依存症臨床は面白いよ」と伝えてきました。しかし返ってきたのは「変わってる」との反応です。そこで,実際に支援者と当事者とを会わせたいと考え,精神保健福祉センターと連携してSMARPP(註1)の地域での実施を始めました。
古賀 SMARPPは依存症患者への治療プログラムですよね。支援者にどう影響するのでしょう。
松本 当事者と直接会い,回復していくプロセスを見ることで,「ダメ。ゼッタイ。」教育で刷り込まれた患者の退廃的なイメージが偏見だと気付けます。そして,積極的な取り組みを行ってくれるようになる。それを見て,私はさらにもう一歩進んで,まさに出所直後の当事者ともスタッフを会わせたくなった。そうして近年取り組んでいるのがVoice Bridges Project(註2)です。両者は,支援者を変革するための取り組みでもあるのですよ。
古賀 例えば長崎大学で取り入れるには何から始めたら良いでしょうか。
松本 タイミングもあるので,焦って導入することはありません。これらのプログラムを大学で実践するよりも,若い先生たちにはぜひ保健行政機関を含め地域のさまざまな施設で経験を積んでほしい。何より,依存症治療が全てではありません。われわれが病院で出合う問題はごく一部に過ぎず,地域では病名がつかず医療機関ではどうしようもない問題が起こり続けています。多様な施設で得た学びを,ぜひ教員として大学へ戻り後進に伝えてください。
古賀 地域での活動は,「ダメ。ゼッタイ。」教育に対して先生が発信なさってきた「刑罰より治療を」の実践でもありますね。
松本 ええ。「ダメ」と否定されることで当事者が周囲に相談できなくなり,声を上げられなくなるのを懸念しています。とは言え,一般の方にどう啓発すべきか容易には答えを出せません。私自身は,周囲が当事者のサポーターになれるような啓発が望ましいと考えていますが,本当に正解かはわからない。しかし,悩み考えることなく,「ダメ。ゼッタイ。」と啓発し続ける社会は間違っているはず。まずは社会全体でもっと議論すべきです。
古賀 いわば体制に逆らう形で,ご苦労も多かったのではないでしょうか。
松本 そうですね。ただ,もちろん根拠なく活動しているのではありません。刑務所や保護観察所のプログラム開発や監修に長年かかわった経験から,「刑罰では絶対治療できない」と感じてのものです。私が活動を続けられるのは,ひとえに当事者の方が支持してくれるから。当事者を置き去りにして,役所や専門家の都合で物事を決定すべきではないですよね。
古賀 違法薬物だけでなく,臨床では市販薬のオーバードーズ(OD)も課題です3)。
松本 近年は若年患者の増加が顕著で多くの死者が出ていますね。これらも乱用防止の教育を行うべきですが,啓発はなかなか進みません。
古賀 啓発の進まない現在,依存行動を繰り返すことで非難を受け,社会から孤立してしまう患者もいるはずです。私は先日,市販薬のODで死に瀕した若い患者を実際に診ました。医師としてどこまで容認しどこから叱り指導すべきか,判断に迷いました。
松本 難しいですよね。ただし,病院に来るほどにまで追い込まれた患者に取るべき態度は明確ではないでしょうか。叱った途端に身構えて敵対的となり,以降は決して正直に告白してくれなくなりますから。やめたいのにやめられない背景に何があるのかを考慮すべきです。
依存症は自殺リスクの高い問題である一方,短期的には自殺に対して抑止的に働いているとも私は考えています。つまり,依存することで死ぬことを延期しているのです。依存を絶つとつらいからこそ,やめられない。そのことを理解して,本人の「やめたい気持ち」と,「やめたくない気持ち」の双方に共感を示すべきでしょう。
松本 その子はきっと,死にたかったんだよね。
古賀 はい。当初は「治療のため」と答えていましたが,後日「死ぬために強い薬を調べて買った」と話してくれました。
松本 世の中が敵意や悪意に満ちていると感じて,「自分は居てはいけない」と思い込み,何を代償にしても苦しみから逃れたくなるほどに追い詰められてしまう。彼らに「ダメだ」と言うからには,われわれは対処法を提案すべきです。それが医師にできるか? 詰まるところ,ぶつかるのは「なぜ死んではならないか」との問いです。依存症や自殺予防に真剣に取り組み続けると,われわれ医師もギリギリまで追い詰められるんだよね。
古賀 そう,そうなんです……。
松本 正直に言えば,死んでいけないことはないと私は思う。彼らの中には,常に他者に振り回され,唯一コントロールできるのが自身の命だけと感じている方もいる。われわれ医療者は,それを取り上げることがいかに残酷かも必ず意識すべきです。患者さんの心は,われわれには縛れません。きれいごとや正論はなんの助けにもならない。その中でわれわれにできることは,「死ぬかどうかはあなたが決めることだけど,『死にたい』の背景にある困り事について,もう少し一緒に考えてみない?」と伝えることだけ。真剣に向き合うほど,「ダメ」とは言えず,「弱ったなぁ」としか言えなくなります。
古賀 松本先生にも,なかなか答えが見つからないのですね。
松本 ええ。とは言え不思議なのは,彼らがわれわれの前で「死にたい」と表出してくれることです。おそらく,その発言も自殺行動も,常に隠したい気持ちと知ってほしい気持ちとの狭間にある。そして,来院して医師と綱引きをしてくれている患者さんは,後者に引き寄せられているのではないでしょうか。
患者さんに明快に答えることが医師として正しいわけではない。論破するのは間違いなく誤りです。むしろ,答えが見つからず困っている姿を見せるのが最も治療的ではないかとすら私は感じます。なぜなら,彼らは正論を吐いたり,根拠なく「こうすべき」と断定する他者に幾度も傷つけられてきたはずだから。弱く失敗し,切れ味の悪い,ありのままの大人の姿を見せてあげるべきかもしれません。
古賀 やはり,正解はない……。自ら飛び込んだ領域ですが,たった3か月の臨床経験の中でさえ,すでに苦しさも感じます。
松本 苦しいよね。これから先生がキャリアを積んでいく中で,ベストを尽くしたはずでも患者を救えない経験がきっとあります。人命にかかわるので,「成長」と軽々しく言うべきではないものの,経験を積んで,耐えて,医師として成長し続けてください。
そのためには,時には互いに愚痴を言い,同じ志の下に切磋琢磨できる仲間が重要です。私は10年ほど前から,井原裕先生(獨協医大)や齋藤環先生(筑波大)などと「よくしゃべる精神科医の会」を開催しています。毎回誰かが話題提供をして,その後飲みに行く。それだけだけど,楽しいですよ。私は依存症を「孤立の病」だとも発信してきましたが4),医師にも所属意識や仲間が必要なのだと思います。
*
古賀 本日はありがとうございました。最後に,私を含めこれから医師として本格的に歩みだす若手にメッセージをお願いします。
松本 どんな分野に進んでも,ぜひ臨床と研究を両立してください。私自身,薬物乱用や自傷患者の診療を一手に担い,その困難を乗り越えるために「リサーチしよう」と研究を始めました。それが現在の診療や活動につながっています。両者を行ったり来たりしながら常に悩み続けることで,大切なことに気づけるはず。ぜひ,臨床的課題解決へのヒントを提唱できる医師になってほしいと思います。
(了)
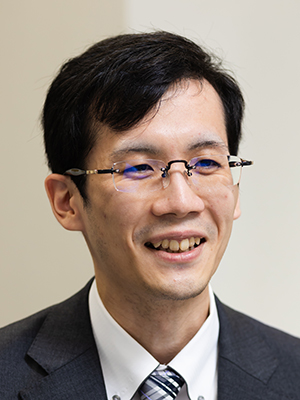 古賀 公基
古賀 公基精神科医となりまだ数か月,未熟未満の初学者ながら,早くも依存症領域に対するスティグマを感じ,回避しようとする自分に焦りと恥を覚えていました。そんな中,松本先生へのインタビューという,後退への一歩を踏みとどまるまたとない機会をいただきました。自らの無知がスティグマを生むことを忘れず学びを続けたいと思います。そして,患者の「死にたい」という言葉の重さ,その苦悩を遠ざけることなく,真摯に向き合い続けていきたいです。
註1:松本俊彦氏を中心に開発された薬物依存症患者への治療プログラム。現在は外来から地域に拡大され,全国の精神保健福祉センターでも実施されている。
註2:保護観察から地域支援へのスムースな移行をめざし,保護観察所と精神保健福祉センターが連携し実施する。精神保健福祉センターの職員が対象者に電話をかけ,支援ニーズの把握や相談支援業務を行う。
1)松本俊彦,他.私を変えた,患者さんの「あのひと言」.週刊医学界新聞3098号.2014.
2)松本俊彦(訳).人はなぜ依存症になるのか.星和書店;2013.
3)嶋根卓也.一般医薬品による薬物依存の実態.週刊医学界新聞3408号.2021.
4)松本俊彦.“孤立の病”依存症,社会に居場所はあるか.週刊医学界新聞3230号.2017.
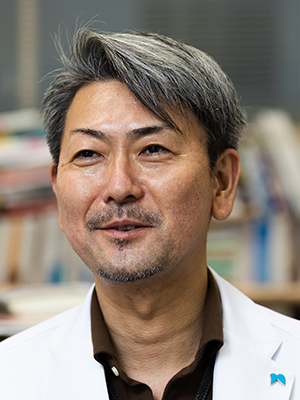
1993年佐賀医大(当時)卒。神奈川県立精神医療センター,横市大病院精神科助手などを経て,2004年に国立精神・神経センター(現・国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所司法精神医学研究部室長に就任。同研究所自殺予防総合対策センター副センター長などを歴任し,15年より薬物依存研究部部長。17年より薬物依存症センターセンター長を併任。『自分を傷つけずにはいられない』(講談社),『誰がために医師はいる』(みすず書房)など著書多数。
引用:医学界新聞
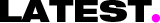

連載:人生二毛作
南米コロンビアへ!! 【連載第3回】
直行では行けない南米 シカゴからコロンビアへ飛ぶ飛行機はマイアミで乗…
2026.03.04 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第5回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2026.02.07 UP

連載:人生二毛作
映画の街 シカゴ!【連載第2回】
まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…
2025.11.21 UP

連載:人生二毛作
世界一周旅、出発の序章 【連載第1回】
さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…
2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント 開催決定!
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に
定期観察 |連載第10回
先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…
2025.07.30 UP
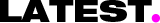

連載:人生二毛作
南米コロンビアへ!! 【連載第3回】
直行では行けない南米 シカゴからコロンビアへ飛ぶ飛行機はマイアミで乗…
2026.03.04 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第5回】自分とク…
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2026.02.07 UP

連載:人生二毛作
映画の街 シカゴ!【連載第2回】
まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…
2025.11.21 UP

連載:人生二毛作
世界一周旅、出発の序章 【連載第1回】
さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…
2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー
Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とク…
皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…
2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に
定期観察 |連載第10回
先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…
2025.07.30 UP
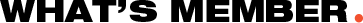
CのMEMBERになると、
オンラインコミュニティでの
MEMBER同士のおしゃべりや
限定コラムやメルマガを
読むことができます。
MEMBER限定のイベントに
参加も可能です!